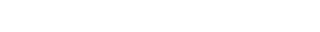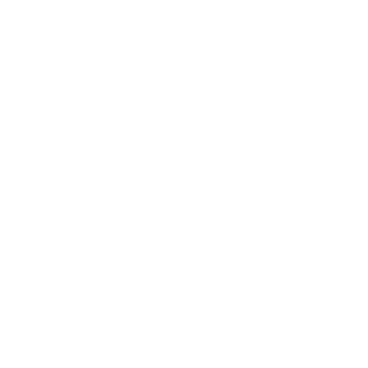
-
露店商は、古代中国における
医薬と農業の神とされる神農を守護神とし、
江戸時代より祭礼やイベントにおいて
子どもから大人まで
庶民が楽しむことのできる
日本の風物として定着してきました。
露店商は大岡越前守こと大岡忠相による
香具師売買・露店行商組合の
公認(享保二十年)に由来すると
されます。 
-
大岡越前守は、十三香具之沙汰(じゅうさんやしのさた)と
呼ばれる新法を定め、承認に許可証を発行するまでに
露店商人は広がっていきました。
その勢いは江戸から遠く離れた小さな村である
秩父までも広がったと言われています。
この時、人が集まるイベントには商売人が集まり、
そしてコミュニティ単位で商売が発展していき、
縁日の露店がメインのイベントに推移し、
消費が高まり都市が拡大したという歴史背景があります。
この歴史背景を踏まえれば「地域内循環経済」が
地域における経済発展の礎となっており、
私たちは、少なからず現代においても
地域経済の発展に寄与したい、この露店商の伝統を守り、
後世に引き継ぎたいという想いや熱意をもって
事業に取り組んでいます。 
-
本組合ではその趣旨に則り、
露店商の古き良き伝統を引き継ぎつつ、
東日本大震災で被災された方々への
炊出し支援や、
京都府内などの
福祉施設等からのご希望に応え、
施設での露店出店等の
ボランティア活動も行っております。
様々な方に露店を楽しんで頂くための
公益活動にも積極的に
取り組んでおります。